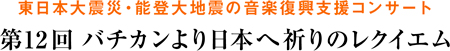![]()

Daniele Agiman(Direttore)
ダニエーレ・アジマン(指揮)
イタリア出身。作曲、ピアノ、合唱指揮、オーケストラ指揮、イタリアオペラ指揮を学び、1991年、マリオ・グゼッラ国際指揮者コンクールで優勝後、マルキジアーナ、トスカーナ、レッチェ、バーリ、トリノといったイタリアのオーケストラや、ヨーロッパの名楽団である、モスクワ放送響、ルーマニア国立サトゥ・マーレフィル、ウクライナ・ハリコフ・フィルなどと協演し、活動を広げた。特に、オーストリアの一流劇場コンツェルトハウスとブルックナーハウスにおける、ウィーン室内管弦楽団との共演で、優れたマエストロの地位を確立。1995年以降は、スイスを代表するルガーノ音楽祭や、コモ・オペラフェスティバル、シチリア島アグリジェント音楽祭など、著名な歌劇場、フェスティバルで「トスカ」「椿姫」「セビリャの理髪師」「蝶々夫人」などのオペラを堂々好演。オペラ指揮者・芸術監督としても、高い評価を得ている。現在は、イタリア最高峰の音楽院として名高い、国立ヴェルディ音楽院オーケストラ指揮科教授、オペラ科主任も務め、ロッシーニ歌劇場管弦楽団常任指揮者としても活躍している。世界中のマスタークラスや、くらしき作陽大学でも教鞭を執った国際派である。過去には指揮教育者コンクールでも優勝し、指導者としての資質も実証済み。“バチカンより日本へ祈りのレクイエム”コンサートは第1回から毎年参加し日本を応援している。

Royal Chamber Orchestra
ロイヤルチェンバーオーケストラ
1987年に今上天皇徳仁陛下を楽団長として設立された「梓室内管弦楽団」に内外の一流オーケストラで活躍した経験のある音楽家が参加し、1993年陛下のご成婚記念CD制作をきっかけに指揮者、堤俊作によって設立された。「ウィーンフィルの奏法」を模範とし、豊かで色彩に富んだ音色による正統的な演奏を理想とし、歴史的解釈を踏まえたヨーロッパの伝統に可能な限り近づく真のオーケストラであることを追求し、精力的に活動している。2005年にはアイルランド、ベルギー、ルクセンブルグ、イタリアの4か国6都市でのヨーロッパツアーを大成功させ、中でもミラノの由緒あるダル・ヴェルメ劇場、ヴィチェンツァの世界遺産オリンピコ劇場でのコンサートは、イタリア人の聴衆から大絶賛された。東京、大阪を中心に活動し、イェルク・デームス、ルチア・アルベルティ、ミッシャ・マイスキー、スタニスラフ・ブーニンなど世界的に活躍する演奏家を招き、そのアンサンブルは聴衆のみならず、演奏家にも絶賛されている。管弦楽はもちろん、オペラ、バレエも得意とし、ヨーロッパの歌劇場管弦楽団のような楽団であるという評価を受けている。2021年3月、2022年4月のオーチャードホール、2023年4月の東京国際フォーラムでの“バチカンより日本へ祈りのレクイエム”公演での演奏は、まさにイタリアの血と情熱を感じさせた。

〈スペシャルゲスト〉
Seiichi Nakajou(Violoncello)
中条 誠一(チェロ)
1989年東京生まれ。桐朋学園大学卒業。その後ハンガリー政府奨学金を得てブダペストのリスト音楽院にてPerényi Miklós氏のもと学ぶ。これまでに小澤征爾音楽塾、Pacific Music Festival、Euro Music Festival、東京・春・音楽祭、リッカルド・ムーティのイタリアンオペラアカデミー等に参加。これまでチェロを藤森亮一、上村昇、毛利伯郎、Perényi Miklós各氏に師事。いしかわミュージックアカデミー2013にてIMA音楽賞、Balassagyarmat international competition2016(Hungary)にて2位受賞。これまでに室内楽をゲルハルト・オピッツ氏や五嶋みどり氏らと、またソリストとしてロイヤルチェンバーオーケストラと共演。高嶋ちさ子withSuperCellistsのメンバー。2022年、コジマ録音よりアルバム「Kedvenceim」、アールアンフィニより「ザ・スーパーチェリスツ」をリリース。

Akiko Yamaguchi(Soprano)
山口 安紀子(ソプラノ)
神戸女学院大学卒業。イタリア国立ヴェルディ音楽院ミラノ声楽科ディプロマ取得、同大学院を首席で修了。第49回日伊声楽コンコルソ優勝のほか、数多くの国際声楽コンクールで上位入賞。スイスのロカルノ劇場『フィガロの結婚』伯爵夫人でデビューし、フォルリ市立歌劇場『蝶々夫人』タイトルロール、その他チェゼーナ市立歌劇場、マントヴァ市立歌劇場、カタルーニャ音楽堂など、欧州各地でオペラやコンサートに出演。国内では藤原歌劇団公演『蝶々夫人』タイトルロールや『仮面舞踏会』アメーリアのほか、市民オペラに於いて『トスカ』『トゥーランドット』タイトルロール、NHK-FM「リサイタル・ノヴァ」や「第九」ソリスト等で出演。二期会会員。

Egle Wyss(Mezzo Soprano)
エグレ・ウィス(メゾ・ソプラノ)
リトアニア出身。ミラノ国立ヴェルディ音楽院に学び、ライン・ドイツ・オペラコンクール特別賞、ジュゼッピーナ・コベッリ国際コンクール第1位、カプリオーロ・フランチャコルタ国際コンクール第1位、ポーランド・アントン・カンピ国際コンクール第1位、2013年BBCカーディフ世界のオペラ歌手ファイナリスト、2016年リトアニアにおける最高のパフォーマンスに送られるゴールデンクロス賞、リトアニア・オペラアワードを「ドン・カルロス」のエボリ公女役で受賞する。この役では、フィレンツェ5月祭歌劇場にて世界を代表するズビン・メータの指揮で大絶賛されている。最近の活躍は、本年1月東京新国立劇場にて「タンホイザー」ヴェーヌス役、エアフルト劇場にて「オルレアンのメイド」ジャンヌダルク役、リトアニア国立劇場にて「カプレーティとモンテッキ」ロメオ役ほか、ミラノ・スカラ座にて「ワルキューレ」にて出演が決まっている。まさに世界のメゾソプラノ歌手を代表する存在である。

Masahiro Shimba(Tenore)
榛葉 昌寛(テノール)
東京藝術大学卒業後、国際ロータリー財団奨学生として国立ミラノ・ヴェルディ音楽院にて学ぶ。テーラモ市立劇場での「椿姫」アルフレード役にてデビューし、その後オペラ、コンサート活動はイタリアのみならずヨーロッパ、アメリカ、カナダなど華々しい。‘13年より毎年“バチカンより日本へ祈りのレクイエム”を総合プロデュースし、東北音楽復興支援をしている。‘13年天皇賞(秋)、‘15年プロ野球日本シリーズ初戦、‘18年日本シリーズの国歌独唱は大絶賛された。掛川市・ペーザロ市の姉妹都市提携にも尽力し、輝け掛川応援大使にも任命されている。バチカンより日本へ祈りのレクイエム総合プロデューサー。
http://www.masahiroshimba.com/

Yoshitaka Murata(Baritono)
村田 孝高(バリトン)
国立音楽大学声楽科卒業。二期会オペラスタジオ・マスターコース第46期修了。藤原歌劇団正会員。‘01年イタリア声楽コンコルソ・シエナ部門入選。日本、イタリア、スロベニア、スペイン、フランスなどで、オペラやコンサートに活躍中。日本では数少ない演技派のバリトンとして評価が高い。サントリーホールにおける小林研一郎氏指揮『第九』をはじめ、ロッシーニ歌劇場とバチカンでのモーツァルト『レクイエム』、ロッシーニ『荘厳ミサ曲』、‘17年ロッシーニ歌劇場管弦楽団来日公演のすべてで、ソリストを務める。‘21年、フィンランドでの初演オペラ『眠る男』でタイトルロールを演じた。
http://baramyu-manatsu.sblo.jp/

〈福島公演〉
Yumi Okazaki(piano)
岡崎 ゆみ(ピアノ)
東京藝術大学卒業、同大学院修了、ピアノ専攻。大学院修士課程2年目の1983年にハンガリー給費留学試験に最優秀で合格し、ハンガリー国立リスト音楽院に留学。Z・コーネル、F・シャンドールの他、マスタークラスにてゾルタン・コチシュ、オキサナ・ヤブロンスカヤ、ジョルジュ・シェベークに師事。1986年朝日新聞主催第5回「新人音楽コンクール」ピアノ部門に優勝。文部大臣賞を受賞。1989年にキングレコードよりデビューCDを発売、その後ソニーレコードからCDを発売、全国でのソロ公演、室内楽、オーケストラ協演を行っている。NHK「おしゃれ工房」、テレビ朝日「USAエクスプレス」を始め多くのテレビ・ラジオ番組で司会を務めた。また、妊婦・乳幼児に向けたコンサートやお芝居仕立ての「音符物語」など、子供に向けたクラシック演奏の活動も多い。紀尾井ホールをはじめ毎年テーマを決めたソロリサイタルを開催している。2019年にはカーネギーホール公演で満席に近い現地の聴衆から大きな拍手が送られた。日本演奏連盟正会員、全日本ピアノ指導者協会正会員。ソニー教育財団評議員。

〈福島公演〉
Chie Nagai(Soprano)
永井 千絵(ソプラノ)
兵庫県朝来市出身。相愛大学音楽学部声楽科卒業。2008年イタリア・ヴェルディ国立音楽院にてS.マンガ氏に師事・ディプロマ取得。相愛大学第18回オペラ「コジファントゥッテ」にドラベッラ役で出演。「2015年リトアニア国立劇場にてオペラ《杉原千畝物語・人道の桜》(世界初演)にサリー・アンナ役で出演。東京オペラプロデュース定期公演、シャルパンティエ作曲「ルイーズ」にスザンヌ役。シャブリエ作曲「エトワール」アスフォデール役。ハイライトシリーズ、「ヘンゼルとグレーテル」グレーテル役。「フィガロの結婚」スザンナ役。江東オペラ「マノン」プセット役、「ロミオとジュリエット」タイトルロールを演じる。国際芸術連盟会員。
【合唱】
●ヒルズ・ロード・コーラス
●池田理代子とばらのミューズたち
●混声合唱団「羽ばたく会」
●富士山と第九を愛する会
●バチカンレクイエム合唱団
〈合唱指導〉大貫浩史